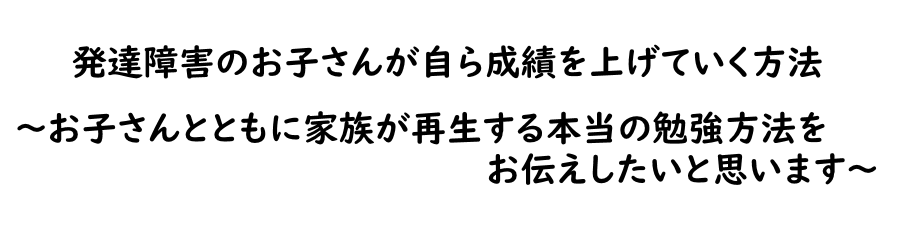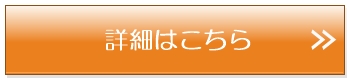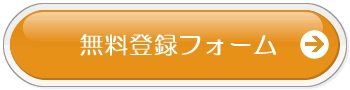『<正常>を救え』のレビュー〜DSM作成者が伝えたかったこととは?
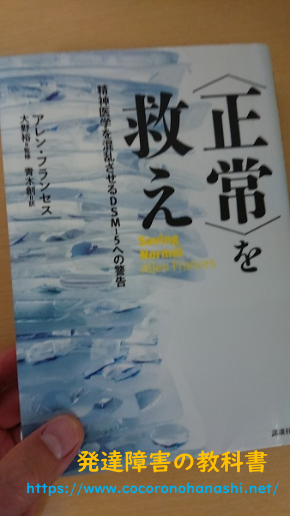
『<正常>を救え』のレビュー〜DSM作成者が伝えたかったこととは?
デューク大学医学部名誉教授であり、DSM−Ⅳの作成委員長であるアレン・フランセスさんのDSM−5への想いが詰まった一冊。
自分のつくった「Ⅳ」が変わってしまったちょっと未練がましいところはありながらも、
Ⅲ〜Ⅳ〜5までの精神医学の変遷がわかるのは面白いですね。
書籍データ
タイトル:『<正常>を救え〜精神医学を混乱させるDSM−5への警告』
原題:Saving Normal
著者:アレン・フランセス
監修:大野裕
訳者:青木創
出版社:講談社
発行年:2013年10月1日
DSMについてはもっと知るべきだったし、この本ももっと早く読むべきだった。
そう思う本です。
DSMの登場は統一性がなく、診断数も極めて少なかった(らしい)状況を一変させます。
診断マニュアルとしての権威が上がれば上がるほど、
発達障害を含めた精神疾患の診断数は「ハイパーインフレ」と表現される増加を見せます。
つまり、ざっくりとアレンさんの指摘するところを説明すると、
精神科を受診する時点で患者さんは人生の中で「最低」の時期にいるわけです。
その「最低」の時期は気持ちも後ろ向きになっていて、
精神疾患としての重い病気の診断基準を満たしやすいということです。
どんなに正しい手順でDSMによる診断をしても、
もう少し様子を見ていれば普通にその人は最低の状態を脱し、上昇していけたかもしれない。
という可能性を見つけることは「不可能」だということです。
人生最低の時、
私たちははやく病院を受診し、その最低の時を脱する効果的で即時的な解決法を医師にもとめます。
その結果、そうなった仮定を踏まえずに、医師と患者だけの部屋での問診で病状が決められます。
それが発達障害も含めた精神疾患のハイパーインフレを引き起こします。
人生に悩むことも、そして、時間をかけて立ち上がることも、私たちは選べるしその力もあるはずなのに。
ちょっと前まではそれが普通であったのに、診断が必要な人のみならず、そうじゃない人まで過剰に診断している。
でも、これは私の考えですが、この過剰な診断が新しい悲劇を生んでしまっている。
適切な支援につながることができなかった女性が自殺してしまった事件がありました。
親御さんも発達障害の疑いを持っていて、その診断を受けようとしても、
医療側が拒否した、というのがざっくりした流れです。
もしも、診断が出ていたら、支援とつながれたかもしれない。
ただ、それはもしかしたら、このDSMによる過剰診断のデメリットの影響で、
間接的に「発達障害の診断が受けられない・診断がおりにくい」という事態を生んだかもしれません。
それを解決するには、私たちひとりひとりが勉強し、
そして、DSMのこと、DSMによってアメリカをはじめとした海外で起こったことを発信していかなくれはいけません。
アレン・フランセスさんもこの著書の中で、
適切な診断を受けるためには自己診断に偏るのはダメだが、自己診断がある程度できるようには、
医師が使うDSMを知っておくべきだとしています。
インターネット上では発達障害はこういう面で苦労があって、だから、こういう支援があるべきだ。
という話ばかりが出てきます。
それはもちろん大事なんです。
だけど、人に頼るだけでは何も解決しません。
地道になりますが、私たちひとりひとりが勉強し、発信していく。
それしかないんです。
こうしないとどういう事態になるか?
アレン・フランセスさんはこうつづります。
「子どもがADHDと診断されるかどうかは、生年月日と非常に深くかかわっているという事実がある。一二月三一日時点の年齢によって学年が変わるという理由だけで、一二月生まれの男児は一月生まれの男児よりリスクが七〇パーセント高くなる。」
日本でいうなら、3月と4月のお子さんの話ですね。
当然、同じ学年なら4月生まれのお子さんと3月生まれのお子さんは、
年齢が小さいほど差が出やすいです。
そんな当たり前のことなのに、
他の子と比べて未熟・未発達ということで発達障害の診断が出てしまうんです。
マニュアルの作成というのは、ひとつにはみんなが読んで納得できる基準ができるということでもありますし、
こうしたマニュアルだけを見てしまって、「当たり前」を見過ごしてしまうことにもなるんです。
また、善意から出た誤った活動もあったんです。
それが「早期発見」です。
早期に発達障害を発見すれば手を打ちやすい。
それは誰しも思うことですし、DSMを作成された方もそうだったと思います。
しかし、現実は発達障害と診断されたお子さんを持つご家庭を混乱させるだけのケースが多かったんです。
子どもの発達はバラバラです。
目安としては○○歳にはこんなことができて、などはります。
それもご家庭によっていろいろ変わります。
お子さんの発達がほぼ100%家庭に依存している時期は、
ご家庭によって子どもの発達はバラバラです。
学校が始まってもすぐにはご家庭の色が抜けるわけではあありません。
何年かかけてやっと違いに自他ともに気づき、すり合わせていく場合のほうが多いと思います。
アメリカは他国と比べるとひとりの人の医療費は2倍高いそうです。
それもあって早期に発見し、未然に防ごうという動きがあった。
そして、それは発達障害においては過剰診断を生んだだけだったんです。
しばらく様子を見ればちゃんと育ったのに、医療の介入、しかも、薬によって事態は悪化し、
結果的に薬はいらなかった、意味のない治療に本人と家族が気がつくまで薬の投与は続いてしまうんです。
本来は善意から始まった。
ざっくりとですが、アレン・フランセスさんの想いとしては、
DSMによって診断が必要な人にきちんと診断がおりること。
そして、DSMをつくることによって患者になる側もそれに目を通し、医師の不適切な医療行為に対して「NO」と言えること。
これを目指されていたんですね。
DSM−Ⅲによって過剰診断が増え、違法ドラッグによる死者よりも、合法ドラッグ(医師が処方する安全に配慮したはずの薬)によって亡くなる人が多いという現実。
その過剰診断をおさえながらも、正しい診断ができるようにという困難な要求のもとに生まれたDSM−Ⅳ。
それはある部分では成功したんですが、DSM−5において過剰診断が一部で復活してしまった。
彼はその部分を嘆いています。
私自身はⅣを読んでいないのでわからないんですが、
アレン・フランセスさんの記述から推測すると「5」は神経科学の最新の知識と研究を用いて、
それまでの精神疾患の常識そのものを変えようとした。
それがうまくいかず、古いもの新しいものがうまく混ざらず、結果として中途半端な診断マニュアルとなり、
過剰診断がまた増えてしまう結果となった。
ということだと思います。
それなりの出来になったⅣをさらに進化させようとして、空回りになったということでしょう。
それでも、発達障害が「神経発達症群」となったのはDSM−5のおかげですし、
Ⅳから5へと受け継がれているものを読み取ろうとしている人はいるのではないか?
と私は思っています。
とにかく、DSMの作成者からみた精神疾患の現実の変遷は読んでいて驚きの連続であり、
日本ではこの大事な流れや事実がまったく入ってきていない、専門家ですら知ろうともしていないということにただただ怖くなるばかりです。
発達障害のお子さんを持つご家庭ばかりではなく、それ以外のご家庭にも読んでおいてほしい話がたくさん載っています。
では、この本のポイントを3つ。
1、発達障害の診断数の増加の悲惨な裏側
アレン・フランセスさんはこう言います。
『ADHDの有病率が上昇したのは、診断などされないほうがいい子どもが「偽陽性」を示して誤診されていることが大きな理由になっている。』
そして、こうして必要がなかったのに薬を投与されたお子さんたちは、
大学生の30%・高校生の10%がテストでいい点をとるためやパーティーを楽しむために精神刺激薬の処方薬を違法に入手するようになったそうなんです。
日本では今まで診断されずに苦しんでいる人が救われたという側面しか皆さん言いません。
しかし、必要のない人が診断され、その薬の効果を知ってしまうと、
その薬に依存するようになるんです。
それは望むべき若者の姿でしょうか?
私たちはそれは考える必要があるのではないでしょうか?
2、自閉症の増加
自閉症は2000人に1人が診断されるものだったのが、
この本が書かれた当時は、80人に1人になっていたそうです。
その当時の韓国では38人に1人という割合になっていたそうです。
そして、この急激な自閉症の診断の増加が新しい悲劇を生みます。
イギリスの医学誌「ランセット」にのちに否定される論文として、
予防接種が自閉症の原因となるのではないか?が登場します。
つまり、診断が増加している時期に偶然にもこの研究が生まれ、
正しいと感じさせるような結果を生んでしまった。
そして、それが今もなお反ワクチンとして引きずっているのではないか?
と私には思えます。
こういった発達障害の診断の急激な増加は、その世界だけにとどまらず、
いろんなところへと見えない影響を与える恐れがあると私たちに教えてくれます。
私たちは面倒でも日々学ばないといけないんですね。
もちろん、自閉症の診断の増加は、必要な子には必要な支援がいくという良い面があります。
でも、反対に不必要にそのレッテルを貼られてしまったお子さんは、
しなくてもいい自己嫌悪や自閉症の子のための支援を受けてしまい、本来、その子の能力を伸ばせるはずの教育を受けられないという負の側面があるんです。
この面を私たち大人は知る必要があると思うんです。
3、正しい診断を受けるには?
簡単にいえば、私たちがDSMを学ぶこと。
医師が間違っている可能性があることを知っておくこと。
こちらの気持ちをきちんと医師にぶつけること。
セカンドオピニオンをもとめること。
そして、きちんとその診断の根拠とその診断を受けた症状についての説明を求めること。
などが、正しいしんだんを受ける方法として書かれています。
そして、こんな風にも言っています。
『しかし、私の知るかぎりでは、精神科医にもとびきり診断が下手な者はおおぜいいるし、看護師やソーシャルワーカーにもとびきり診断が上手な者はいる。したがって免許証だけで決められない。職種間のちがいよりも、職種内のちがいのほうが大きい。だからこそ、賢い消費者となって自分の問題を勉強し、あなた(と家族)が事実上のセカンドオピニオンの提供役と処置の監視役をつとめなければならない。』
とあります。
DSMの作成された方みずからが、医師でも信用のできない人はいるし、医師じゃなくてもちゃんとわかっている人はいると言っています。
この指摘はとても大事だと思います。
これが正しい診断を受けるうえで大事なことですね。
デメリットはある??
DSM−Ⅳの作成者であるので、
DSM−5の新しい試みに対して辛口すぎるところがある、ということですね。
過剰診断をおさせることに一定の評価があるⅣと、
それを踏まえて新しい枠組みをつくろうとしてできなかった5。
確かに、アレン・フランセスさんにとっては納得できないものもあるんでしょうが、
発達障害というのが「神経発達症群」という言葉になったことは1つの収穫だと思っています。
メリットは??
日本の不勉強な医師たちのことがわかる本です。
自衛のために買ったほうがいいです。
アメリカはDSMを読んだうえで議論になっているのに、
日本では読みもしないで過剰診断がくだされます。
DSM自体の存在が無視されていることが多いので、
過剰診断が発達障害の中で起こっているということすら知らない人が大勢います。
自分と家族を守るためには読んでおきたい本ですし、
この本のことをは広めていきたいですね。
あなたを守るものは最終的にはあなたですし、
自分自身を一番守れるものは知識だと思っています。
この本はあなたの力になってくれる本ですよ。
DSMを知らなくてもここから読めば、
いつかDSMに触れた時により理解が深まると思います。
ぜひ、このレビューを読まれたなら手にとり読んでください。